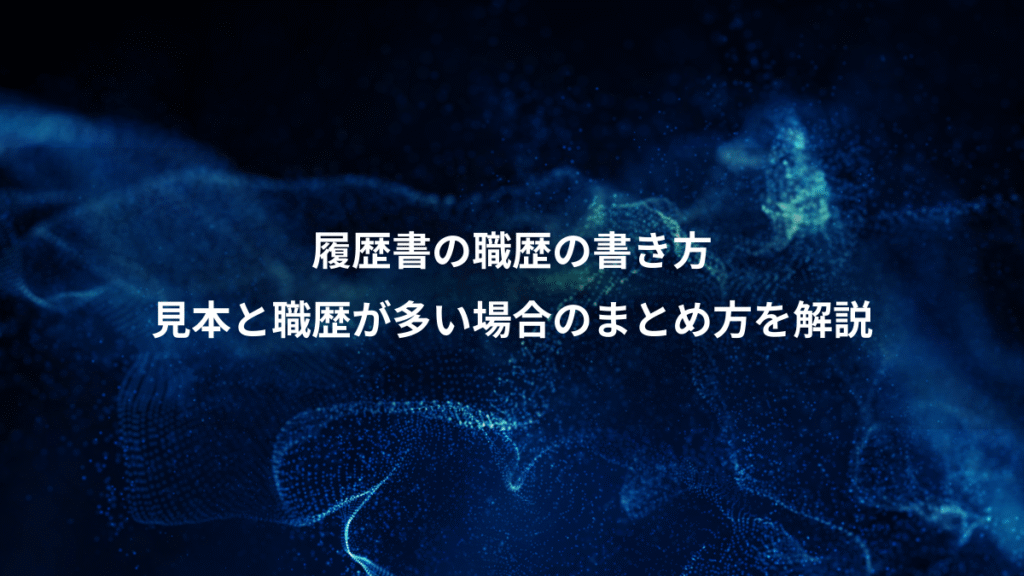履歴書は、あなたのキャリアを企業の採用担当者に伝えるための最初の、そして最も重要な書類です。その中でも「職歴」の欄は、これまでの経験やスキル、仕事への取り組み方をアピールする中心的な要素となります。しかし、「どこまで詳しく書けばいいのか」「転職回数が多い場合はどうすれば?」「ブランク期間はどう説明する?」など、多くの人が書き方に悩む部分でもあります。
この記事では、履歴書の職歴欄を完璧に仕上げるための9つの基本ルールから、雇用形態別、さまざまなケース別の具体的な書き方まで、豊富な見本とともに徹底的に解説します。さらに、職務経歴書との違いや、多くの人が抱く疑問に答えるQ&A、便利な作成ツールまで網羅しました。
この記事を最後まで読めば、あなたの経歴が持つ価値を最大限に引き出し、採用担当者の目に留まる、説得力のある履歴書を作成できるようになるでしょう。
目次
履歴書の職歴を書く前に押さえるべき9つの基本ルール
職歴欄の作成に取り掛かる前に、まずは誰にでも共通する基本的なルールを理解しておくことが不可欠です。これらのルールは、採用担当者が履歴書をスムーズに読み解き、あなたの経歴を正確に評価するための土台となります。一つひとつのルールには明確な理由があり、これらを守ることで、丁寧で信頼性の高い人物であるという印象を与えることができます。ここでは、職歴欄の根幹をなす9つのルールを、具体的な書き方のポイントや注意点とともに詳しく解説します。
① 学歴の下に1行空けて中央に「職歴」と書く
履歴書のフォーマットは、情報を整理し、見やすくするための工夫が凝らされています。学歴と職歴は、あなたの経歴を時系列で示す重要な項目ですが、これらが混在していると非常に読みにくくなります。
まず、学歴欄をすべて書き終えたら、必ず1行分の空白を設けてください。この1行が、学歴と職歴という異なるセクションを明確に区切る役割を果たします。そして、空けた行の次の行の中央に「職歴」と見出しを記載します。この中央揃えの「職歴」という見出しがあることで、採用担当者はここから職務経 ‘data’ in self”履歴が始まると一目で認識できます。
【書き方のポイント】
- 学歴の最終行(例:「〇〇大学 〇〇学部 卒業」)を書き終える。
- 次の行を1行、完全に空ける。
- その次の行の、左右中央の位置に「職歴」とだけ書く。
【なぜこのルールが重要なのか】
- 視認性の向上: 学歴と職歴が明確に区別されることで、採用担当者は情報を素早く正確に把握できます。何十、何百という履歴書に目を通す担当者にとって、この読みやすさは非常に重要です。
- ビジネスマナーの証明: 定められたフォーマットや慣習に沿って書類を作成できることは、基本的なビジネスマナーが身についていることの証明になります。細部への配慮ができる人材であるというポジティブな印象につながります。
もし、学歴と職歴が同じ欄にまとまっているタイプの履歴書を使用している場合でも、このルールは同様に適用されます。学歴を書き終えたら1行空け、中央に「職歴」と記してから、具体的な職務経歴を書き始めましょう。この小さな一手間が、あなたの履歴書全体の完成度を高める第一歩となります。
② 年月は西暦か和暦で統一する
履歴書全体で、年月日の表記方法を統一することは、基本中の基本でありながら非常に重要なルールです。学歴欄で和暦(平成、令和など)を使ったのであれば、職歴欄も和暦で統一します。同様に、西暦(2020年など)で書き始めたら、最後まで西暦で通してください。
和暦と西暦が混在している履歴書は、採用担当者にとって時系列の把握が困難になり、非常に読みにくいものになります。「この人は注意力散漫なのではないか」「基本的なルールを守れない人なのかもしれない」といった、不要なマイナスイメージを与えかねません。
【どちらを選ぶべきか?】
基本的には、西暦と和暦のどちらを使用しても問題ありません。ただし、応募する業界や企業によって好まれる傾向が異なる場合があります。
- 西暦が好まれる傾向: IT業界、外資系企業、ベンチャー企業など、グローバルな視点や先進性が重視される分野では西暦が一般的です。
- 和暦が好まれる傾向: 官公庁、金融機関、歴史のある伝統的な日本企業などでは、和暦が用いられることが多いです。
迷った場合は、企業の公式サイトの会社概要や沿革の年号表記を参考にするのがおすすめです。企業が使用している表記に合わせることで、細やかな配慮ができるという印象を与えられます。もし判断がつかなければ、ビジネスシーンで広く使われ、年齢計算もしやすい西暦で統一しておくのが無難と言えるでしょう。
【注意点】
- 生年月日との統一: 履歴書の冒頭に記載する生年月日欄の表記も、学歴・職歴欄と必ず統一してください。
- 元号の切り替わり: 和暦を使用する場合、元号が変わるタイミング(平成から令和など)に注意が必要です。例えば、平成31年4月まで存在し、令和元年は5月1日からです。こうした点を間違えないようにしましょう。
- 年の自動計算ツール: 自身の入学・卒業年次などを正確に把握するために、Web上で提供されている年号・西暦の自動計算ツールなどを活用すると、間違いを防げます。
表記の統一は、あなたの丁寧さと注意力を示す試金石です。提出前に必ず全体を見直し、和暦と西暦が混在していないか最終チェックを行いましょう。
③ 会社名は(株)などと省略せず正式名称で書く
職歴欄に記入する会社名は、必ず登記上の正式名称で記載する必要があります。日常的に使っている略称や通称(例:「〇〇銀行」)、(株)や(有)といった略語は、ビジネス文書である履歴書では不適切です。
例えば、「株式会社〇〇商事」が正式名称であれば、その通りに記載します。これを「(株)〇〇商事」や「〇〇商事」と省略してはいけません。これは、あなたが過去に所属していた組織に対して敬意を払うとともに、正確な情報伝達を重視する姿勢を示すことにつながります。
【正式名称の確認方法】
会社の正式名称がうろ覚えの場合は、必ず以下の方法で確認しましょう。
- 会社の公式サイト: サイトの下部にあるフッターや、「会社概要」「企業情報」といったページに正式名称が記載されています。
- 名刺: 在職中にもらった名刺があれば、そこに正式名称が記載されています。
- 国税庁 法人番号公表サイト: 法人番号を入力または検索することで、正式な商号(社名)を確認できます。参照:国税庁 法人番号公表サイト
【書き方の見本】
| 悪い例 | 良い例 |
|---|---|
| (株)ABC | 株式会社ABC |
| 〇〇(株) | 〇〇株式会社 |
| (有)山田製作所 | 有限会社山田製作所 |
| NPO法人ケアサポート | 特定非営利活動法人ケアサポート |
このように、株式会社の位置(前株か後株か)や、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、学校法人といった法人格も正確に記載することが求められます。
【なぜ正式名称が重要なのか】
採用担当者は、記載された会社名をもとに、あなたがどのような規模や業種の企業で、どのような経験を積んできたのかを把握します。また、社会保険の手続きなど、入社後の事務処理においても、あなたの経歴は重要な情報となります。不正確な会社名は、経歴照会(リファレンスチェック)の際に齟齬を生じさせる原因にもなりかねません。
たかが会社名と思わず、一つひとつの情報を正確に記述する意識が、あなたの信頼性を高める上で非常に重要です。
④ 雇用形態を明記する
正社員以外の雇用形態(契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど)で勤務していた場合は、会社名の後ろに雇用形態を明記することが必須です。これを怠ると、経歴を偽っていると誤解されたり、採用担当者があなたのキャリアプランを正確に理解できなかったりする可能性があります。
【書き方のポイント】
会社名の後ろにカッコ書きで「(契約社員)」「(アルバイト)」のように記載するのが一般的です。
【見本】
平成〇〇年〇月 株式会社〇〇 入社(契約社員として)
令和〇〇年〇月 〇〇レストラン 入社(アルバイト)
【なぜ雇用形態の明記が重要なのか】
- 経歴の透明性: どのような立場で業務に携わってきたのかを正直に伝えることで、誠実な人柄をアピールできます。雇用形態を意図的に隠すような書き方は、採用担当者に不信感を与えます。
- 経験の適切な評価: 採用担当者は、雇用形態によって任される業務の範囲や責任の度合いが異なることを理解しています。雇用形態を明記することで、あなたの経験やスキルを文脈に沿って正しく評価してもらえます。例えば、契約社員としての専門業務や、アルバイトでの接客経験など、その立場だからこそ得られた強みを的確に伝えることができます。
- キャリアプランの明確化: 過去の雇用形態の変遷は、あなたのキャリアに対する考え方を反映している場合があります。例えば、「専門スキルを身につけるために、まずは契約社員として経験を積んだ」といったストーリーを採用面接で語る際にも、履歴書の記載がその裏付けとなります。
特に、正社員経験がない場合や、非正規雇用の経験をアピールしたい場合は、雇用形態の明記が不可欠です。パートやアルバイトの経験であっても、応募職種に関連するものであれば立派なアピール材料になります。正直かつ正確に記載し、自信を持って自分のキャリアを伝えましょう。
⑤ 部署名や役職名も正確に書く
会社名だけでなく、所属していた部署名や役職名も正確に記載しましょう。これにより、あなたが組織の中でどのような役割を担い、どのような専門分野で業務を行っていたのかが具体的に伝わります。
【書き方のポイント】
入社した会社の行の次に、所属部署を記載するのが一般的です。役職に就いていた場合は、その役職名も併記します。部署異動や昇進があった場合は、その年月と新しい部署・役職名を時系列に沿って追記することで、キャリアアップの過程を効果的に示すことができます。
【見本:部署名のみ】
平成〇〇年〇月 株式会社〇〇商事 入社
営業部 配属
【見本:役職・昇進あり】
平成〇〇年〇月 株式会社〇〇テクノロジー 入社
開発第一部 配属
令和〇〇年〇月 同部署 主任に昇進
【なぜ部署名・役職名が重要なのか】
- 専門性の具体化: 「営業部」と書けば営業経験が、「経理部」と書けば経理経験があることが一目瞭然です。これにより、あなたの専門スキルが応募職種とどう関連するのか、採用担当者がイメージしやすくなります。
- キャリアパスの可視化: 部署異動や昇進・昇格の履歴は、あなたが企業内でどのように評価され、成長してきたかを示す客観的な証拠です。「主任に昇進」「マネージャーに就任」といった記載は、リーダーシップやマネジメント能力のアピールに直結します。
- 業務内容の説得力向上: 次のルールで解説する「業務内容」の記述も、所属部署が明確であることで、その内容に説得力が増します。例えば、「新規顧客開拓」という業務内容も、「法人営業部」という部署名とセットになることで、より具体的なイメージが湧きます。
部署名が長くて1行に収まらない場合は、無理に詰め込まず、改行して見やすく記述しましょう。正確な部署名や役職名が思い出せない場合は、当時の辞令や組織図、社内報などを確認するか、元同僚に問い合わせるなどして、できる限り正確な情報を記載するよう努めてください。
⑥ 業務内容を簡潔に記載する
所属部署や役職名に加えて、具体的にどのような業務を担当していたのかを簡潔に記載することで、職歴の価値は格段に上がります。採用担当者は、あなたが単に「営業部にいた」という事実だけでなく、「営業部で何をしていたのか」という具体的な中身を知りたいと考えています。
【書き方のポイント】
部署名や役職名を記載した下の行に、1〜2行程度で簡潔にまとめます。応募する職種で活かせる経験やスキルを中心に記載するのが効果的です。具体的な数字(実績)を盛り込むと、より説得力が増します。
【見本】
平成〇〇年〇月 株式会社〇〇商事 入社
営業部 配属
法人向けに自社システムの新規開拓営業に従事。
(年間売上目標120%を3年連続で達成)
【何を記載すべきか】
- 職務内容: 誰に対して(Who)、何を(What)、どのように(How)行っていたのかを具体的に書きます。(例:「中小企業向けに、会計ソフトの導入支援およびコンサルティングを担当」)
- 実績・成果: 数値で示せる実績があれば積極的に記載しましょう。(例:「担当エリアの売上を前年比15%向上」「5名のチームマネジメントを経験」)
- 使用ツール・技術: 応募職種に関連する専門的なツールやソフトウェア、プログラミング言語などの使用経験もアピールになります。(例:「Salesforce、Excel(VBA)、PowerPointを使用」)
【注意点】
業務内容の記載は、あくまで「簡潔に」が原則です。詳細な業務内容や実績、自己PRは職務経歴書に記載するべき内容です。履歴書の職歴欄では、あなたのキャリアの要点を伝えることに専念しましょう。長々と書きすぎると、かえって要点がぼやけてしまい、読みにくくなるため注意が必要です。
この業務内容の記述は、あなたの経験をアピールする絶好の機会です。応募先の企業が求めている人物像を意識し、それに合致する経験を戦略的に選び出して記載しましょう。
⑦ 退職理由は簡潔に書く
退職した会社については、その理由を記載する必要があります。ここで重要なのは、退職理由を正直かつ簡潔に書くことです。ネガティブな理由であっても、それをポジティブな表現に転換する工夫が求められます。
【基本的な書き方】
- 自己都合の場合: 「一身上の都合により退職」と記載するのが一般的です。面接で詳細を聞かれた際に、キャリアアップや新しい挑戦への意欲など、前向きな理由を説明できるように準備しておきましょう。
- 会社都合の場合: 会社の倒産、事業所の閉鎖、解雇(リストラ)などの場合は、「会社都合により退職」と明確に記載します。これは自己都合ではないため、正直に書くことで、選考で不利になることはありません。
【見本】
令和〇〇年〇月 株式会社〇〇 一身上の都合により退職
令和〇〇年〇月 株式会社△△ 会社都合により退職(事業部縮小のため)
【ネガティブな理由の伝え方】
たとえ「人間関係が悪かった」「給与に不満があった」といったネガティブな理由で退職した場合でも、それをそのまま履歴書に書くのは避けるべきです。採用担当者に「同じ理由でまた辞めるのではないか」という懸念を抱かせてしまいます。
面接で聞かれた場合に備え、ネガティブな事実をポジティブな動機に変換しておくことが重要です。
| ネガティブな事実 | ポジティブな変換例(面接での回答) |
|---|---|
| 残業が多くて疲弊した | 「より効率的に成果を出し、ワークライフバランスを保ちながら長期的に貢献できる環境で働きたいと考えました」 |
| 人間関係に悩んだ | 「チームとしての一体感を持ち、協調性を発揮しながら目標達成を目指せる職場で自分の力を試したいと思いました」 |
| スキルアップが見込めなかった | 「現職で得た基礎スキルを活かし、より専門性の高い業務に挑戦することで、貴社に貢献できるレベルまで成長したいと考えています」 |
履歴書には「一身上の都合により退職」とだけ書き、その背景にある前向きな転職理由を自分の言葉で語れるように準備しておくことが、円滑な選考プロセスにつながります。
⑧ 在職中の場合は「現在に至る」と書く
転職活動は、必ずしも退職後に行うとは限りません。在職中に次の職場を探している場合は、職歴の書き方が少し異なります。
現在もその会社に勤務していることを明確に伝えるために、最後の職歴の行に「現在に至る」または「在職中」と記載します。これにより、採用担当者はあなたがまだその会社に籍を置いていることを正確に把握できます。
【書き方のポイント】
最後の職歴として、現在所属している会社の入社年月日、会社名、部署名などを記載します。その次の行に、左詰めで「現在に至る」または「在職中」と書きます。どちらの表現を使っても問題ありませんが、「現在に至る」がより一般的です。
【見本】
平成〇〇年〇月 株式会社〇〇 入社
マーケティング部 配属
Webサイトのコンテンツ企画・制作を担当
現在に至る
【なぜ「現在に至る」と書くのか】
- 状況の明確化: この記載がないと、採用担当者はあなたがすでに退職しているのか、それとも在職中なのか判断できません。入社可能時期の調整や、現職への連絡の配慮(就業時間中の連絡を避けるなど)にも関わるため、正確な状況を伝えることが重要です。
- 退職予定日の補足: もし退職日がすでに決まっている場合は、「現在に至る」の後にカッコ書きで追記すると、より親切です。
例:現在に至る(令和〇年〇月〇日 退職予定)
これにより、採用担当者は入社可能時期を具体的に把握でき、選考プロセスをスムーズに進めることができます。
「現在に至る」と記載した場合は、その下に「以上」と書くのを忘れないようにしましょう。
⑨ 最後に「以上」と右詰めで書く
職歴をすべて書き終えたことを明確に示すために、最後の行に「以上」と記載します。これは、職歴欄の締めくくりの合図であり、「これ以上、記載する職歴はありません」という意思表示になります。
【書き方のポイント】
最後の職歴(退職した会社の場合は「一身上の都合により退職」、在職中の場合は「現在に至る」)を書き終えたら、次の行の右端に「以上」と記載します。左詰めや中央揃えではなく、必ず右詰めにしてください。
【見本:退職済の場合】
...(最後の職歴)...
令和〇〇年〇月 株式会社〇〇 一身上の都合により退職
以上
【見本:在職中の場合】
...(現在の職歴)...
現在に至る
以上
【なぜ「以上」が必要なのか】
- 記載終了の明示: これにより、職歴の記載がここで終わりであることが明確になります。もし「以上」の記載がないと、書き忘れや記入漏れがあるのではないかと採用担当者に思われる可能性があります。
- 改ざん防止: 書類に「以上」と記載することで、後から何者かによって情報が不正に追記されることを防ぐ意味合いもあります。これは、ビジネス文書全般で用いられる慣習の一つです。
学歴欄を書き終えた際にも、同様に最後の行の右詰めに「以上」と記載します。ただし、学歴と職歴が同じ欄にまとまっている形式の履歴書の場合は、学歴の最後には「以上」をつけず、職歴をすべて書き終えた後に一度だけ「以上」を記載します。
これらの9つの基本ルールは、あなたの履歴書をプロフェッショナルなものにするための基礎です。これらのルールを確実に守ることが、採用担当者からの信頼を得るための第一歩となります。
【見本でわかる】雇用形態別の職歴の書き方
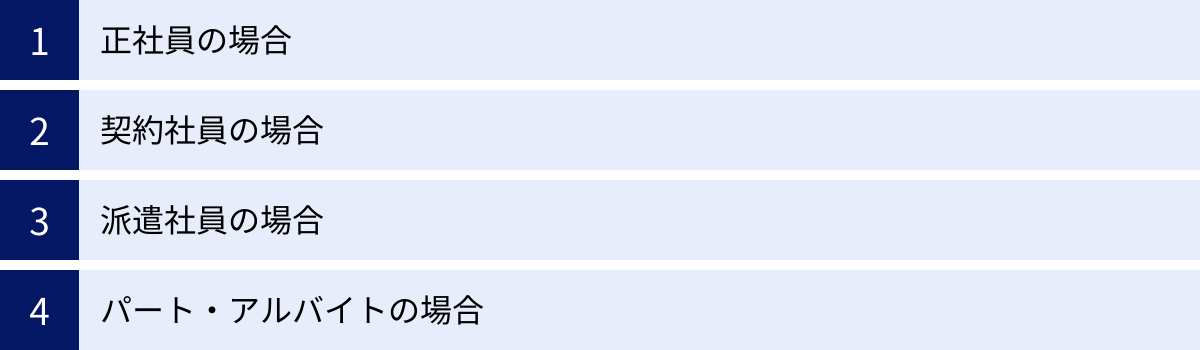
これまでのキャリアは、正社員経験だけとは限りません。契約社員として専門性を高めたり、派遣社員として多様な職場を経験したり、あるいはパート・アルバイトで柔軟な働き方をしながらスキルを磨いたりと、働き方は人それぞれです。ここでは、雇用形態別に職歴の書き方のポイントと具体的な見本を紹介します。それぞれの立場で得た経験を効果的にアピールする方法を学びましょう。
正社員の場合
正社員としての経歴は、キャリアの中心となる最も重要な情報です。安定した雇用のもとで、どのような責任を担い、どのような成果を上げてきたかを明確に示すことが求められます。
【書き方のポイント】
- 雇用形態の記載は不要: 正社員の場合、特に雇用形態を記載する必要はありません。会社名を書くだけで、一般的に正社員として解釈されます。
- 部署名・役職名は必須: 所属部署や役職名を正確に記載し、組織内での役割を明確にします。
- 業務内容で具体性を持たせる: 担当した業務内容を簡潔に記述し、どのようなスキルや経験があるのかをアピールします。可能であれば、実績を数値で示すと説得力が増します。
- 昇進・異動はキャリアアップの証: 昇進や部署異動があった場合は、年月とともに必ず記載しましょう。これはあなたの成長や会社からの評価を示す重要な情報です。
【見本】
職歴
平成28年 4月 株式会社ABC商事 入社
営業第一部に配属
首都圏エリアの法人顧客に対し、オフィス機器の提案営業に従事。
平成31年 4月 同部 主任に昇進
3名のメンバーの育成指導を担当。
令和 3年 4月 マーケティング部に異動
新商品のプロモーション戦略の立案および実行を担当。
令和 5年 3月 一身上の都合により退職
以上
【解説】
この見本では、入社から退職までのキャリアの流れが時系列で明確に示されています。「主任に昇進」「マーケティング部に異動」といった記述により、単なる営業担当者から、マネジメント経験やマーケティングスキルを持つ人材へと成長した過程がわかります。業務内容も簡潔に記載されており、採用担当者はこの人物が持つスキルセットを容易に想像できます。このようにキャリアの変遷を具体的に示すことが、正社員の職歴をアピールする上での鍵となります。
契約社員の場合
契約社員は、有期雇用契約に基づき、特定のプロジェクトや専門業務に従事することが多い働き方です。そのため、職歴欄では「なぜ契約社員として働いていたのか」そして「そこでどのような専門性を身につけたのか」を伝えることが重要になります。
【書き方のポイント】
- 雇用形態を明記: 会社名の後ろに「(契約社員)」または「(契約社員として入社)」と必ず記載します。
- 専門性をアピール: 担当した業務内容を具体的に書き、専門スキルをアピールします。契約期間が定められていた理由(例:特定のプロジェクトのため)が明確であれば、それを補足するのも良いでしょう。
- 契約満了の記載: 契約期間が満了して退職した場合は、「契約期間満了により退職」と記載します。これにより、自己都合での短期間の退職ではないことが明確になり、ポジティブな印象を与えます。正社員登用を目指しての転職活動など、前向きな理由がある場合は、面接で伝えられるように準備しておきましょう。
【見本】
職歴
令和 2年 4月 株式会社ウェブデザインスタジオ 入社(契約社員)
Webデザイナーとして、大手化粧品会社のキャンペーンサイト制作プロジェクトに従事。
(HTML, CSS, JavaScript, Photoshop, Illustratorを使用)
令和 5年 3月 契約期間満了により退職
以上
【解説】
この見本では、まず「(契約社員)」と雇用形態を明記しています。業務内容では「大手化粧品会社のキャンペーンサイト制作プロジェクト」と具体的な業務を、「HTML, CSS…」と使用スキルを記載することで、専門性の高さをアピールしています。そして、退職理由を「契約期間満了により退職」とすることで、計画的にキャリアを積んできた印象を与えています。契約社員としての経験は、特定の分野での即戦力性をアピールする絶好の機会です。
派遣社員の場合
派遣社員の経歴は、派遣元(雇用契約を結んでいる派遣会社)と派遣先(実際に業務を行った会社)の両方を記載する必要があるため、少し複雑になります。正しい書き方をしないと、経歴が分かりにくくなるため注意が必要です。
【書き方のポイント】
- 派遣元を明記: まず、派遣会社に登録した年月と会社名を記載します。
- 派遣先と業務内容を記載: 次に、派遣先企業の会社名、部署、派遣期間、具体的な業務内容を記載します。「〇〇株式会社に派遣」「〇〇部にて勤務」のように、派遣である旨が分かるように書きます。
- 複数の派遣先がある場合: 派遣先ごとにまとめて記載します。派遣期間が終了したら、「派遣期間満了」と記載します。
- 守秘義務に注意: 派遣契約によっては、派遣先の企業名を公にすることが禁じられている場合があります。その際は「大手通信会社」「外資系製薬会社」のように、業種や企業規模が分かる範囲でぼかして記載し、面接で口頭で説明できるようにしておきましょう。事前に派遣元の担当者に確認するのが確実です。
【見本】
職歴
平成30年 5月 株式会社スタッフサービスに派遣登録
令和 1年 6月 株式会社テックソリューションズに派遣
経理部にて、月次決算補助、請求書発行業務に従事。
(使用ソフト:勘定奉行、弥生会計)
令和 3年 5月 派遣期間満了
令和 3年 7月 グローバル製薬株式会社に派遣
人事部にて、採用アシスタント業務を担当。
現在に至る
以上
【解説】
この見本では、まず派遣元である「株式会社スタッフサービス」に登録したことを示し、その後に各派遣先での経歴を時系列で記載しています。派遣先ごとに「会社名」「部署」「業務内容」がセットで書かれているため、どこで何をやっていたのかが非常に分かりやすいです。多様な業界や職場で経験を積めるのが派遣社員の強みです。その経験の幅広さや、異なる環境への適応能力をアピールできるよう、情報を整理して記載しましょう。
パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトの経験も、特に社会人経験が浅い場合や、応募職種に直結する経験である場合には、重要なアピールポイントになります。ただし、すべてのアルバイト歴を羅列する必要はありません。戦略的に記載することが求められます。
【書き方のポイント】
- 応募職種との関連性を重視: 応募する仕事内容と関連性の高い経験を優先して記載します。例えば、事務職に応募するならデータ入力のアルバイト、販売職に応募するならアパレルショップのアルバイト経験は有効なアピールになります。
- 雇用形態を明記: 会社名の横に「(アルバイト)」「(パートタイム勤務)」などと必ず記載します。
- 短期間のものは省略も可: 1〜2ヶ月で辞めたアルバイトなど、アピールにつながらない短期間のものは、無理に記載する必要はありません。職歴に一貫性を持たせることを意識しましょう。
- 社会人経験がある場合: すでに正社員としての職歴が十分にある場合は、アルバイト歴は省略するのが一般的です。ただし、ブランク期間中のアルバイトなど、説明が必要な場合は記載を検討します。
- 業務内容で貢献度を示す: 「レジ打ち」だけでなく、「後輩アルバイトの指導を担当」「売上目標達成に貢献」など、主体的に取り組んだことや成果を簡潔に加えると、評価が高まります。
【見本】
職歴
平成29年 4月 カフェ・ド・〇〇 新宿店 入社(アルバイト)
接客、レジ業務、ドリンク作成を担当。
新人スタッフのトレーニングも担当し、店舗のスムーズな運営に貢献。
令和 2年 3月 一身上の都合により退職
以上
【解説】
この見本では、「(アルバイト)」と明記した上で、単なる作業内容だけでなく「新人スタッフのトレーニングも担当」という主体的な行動を加えることで、責任感やリーダーシップをアピールしています。たとえアルバイトであっても、そこで何を得て、どのように貢献したのかを自分の言葉で語ることができれば、それは立派な職務経歴です。応募先で活かせる経験は何か、という視点で記載するアルバイト歴を選びましょう。
【ケース別】状況に応じた職歴の書き方と見本
キャリアは一直線とは限らず、人によってさまざまな事情があります。「転職回数が多い」「ブランク期間がある」「短期間で辞めてしまった」など、履歴書にどう書けばいいか悩むケースも少なくありません。しかし、書き方一つでネガティブに見えがちな経歴も、見方を変えれば強みとしてアピールできます。ここでは、多くの人が悩むであろう特殊なケース別に、具体的な書き方と見本、そして採用担当者に与える印象を好転させるためのポイントを詳しく解説します。
転職回数が多い・職歴が書ききれない場合
転職回数が多いこと自体が、一概に不利になるとは限りません。多様な環境で経験を積んだ「適応能力の高さ」や、幅広いスキルを持つ「ゼネラリスト」としての価値をアピールできる可能性があります。問題は、その経歴をいかに分かりやすく、ポジティブに伝えるかです。
【書き方のポイント】
- すべての職歴を正直に書くのが原則: 経歴詐称を疑われないためにも、原則としてすべての職歴を記載します。
- 職務経歴書への誘導: 履歴書の職歴欄は、スペースが限られています。そこで、業務内容の詳細は職務経歴書に譲るという戦略をとります。履歴書には会社名、在籍期間、部署名など基本的な情報のみを記載し、「※業務内容の詳細は、職務経歴書をご参照ください。」と一文を添えるのが効果的です。これにより、履歴書がすっきりと見やすくなります。
- アピールしたい職歴を強調: 応募職種に特に関連の深い職歴については、業務内容を簡潔に1行だけ記載し、他の職歴は省略するなど、メリハリをつけるのも一つの手です。
- 一貫性のあるストーリーを作る: なぜ転職を繰り返したのか、その背景にあるキャリアプラン(例:「〇〇の専門家になるために、△△と□□のスキルを段階的に習得する必要があった」など)を面接で語れるように準備しておくことが何よりも重要です。
【見本:職務経歴書へ誘導するパターン】
職歴
平成25年 4月 株式会社A 入社 営業部配属
平成27年 9月 一身上の都合により退職
平成27年10月 株式会社B 入社 企画部配属
平成30年 3月 一身上の都合により退職
令和 1年 4月 株式会社C 入社 マーケティング部配属
令和 4年 8月 一身上の都合により退職
※各社での業務内容の詳細は、別途提出の職務経歴書をご参照ください。
以上
【解説】
この書き方であれば、職歴が多くてもスペース内に収まり、かつ正直にすべての経歴を開示していることになります。採用担当者も「詳細は職務経歴書を見ればいいのだな」と理解し、スムーズに選考を進めることができます。大切なのは、転職の多さを隠すのではなく、それを「多様な経験」という強みに転換するための見せ方を工夫することです。
職歴にブランク(空白期間)がある場合
病気療養、家事・育児、介護、留学、資格取得の勉強など、さまざまな理由で職歴にブランク(空白期間)が生まれることがあります。採用担当者はこの期間について「何をしていたのか」「働く意欲に問題はないか」という点に関心を持ちます。正直に、かつポジティブに説明することが重要です。
【書き方のポイント】
- ブランク期間を隠さない: 職歴の年月をごまかしてブランクがないように見せかけるのは絶対にやめましょう。入社後に社会保険の加入履歴などで必ず発覚し、経歴詐称として問題になります。
- 理由を簡潔に記載する: 職歴欄に、ブランク期間とその理由を簡潔に記載します。これにより、採用担当者の疑問を事前に解消できます。
- ポジティブな表現を心がける: たとえネガティブな理由(病気療養など)であっても、「現在は完治しており、業務に支障はありません」と付け加えることで、働く意欲と能力があることを示します。資格取得や留学など、スキルアップにつながる活動をしていた場合は、絶好のアピールチャンスです。
【見本:ケース別の書き方】
| ケース | 書き方の見本 | ポイント |
|---|---|---|
| 資格取得 | 令和3年4月~令和4年3月 ファイナンシャルプランナー2級の資格取得のため勉強に専念 |
スキルアップへの意欲をアピールできる。取得した資格名も明記する。 |
| 留学 | 令和2年10月~令和3年9月 語学力向上のためカナダへ留学(ビジネス英語を習得) |
目的と成果(何を習得したか)を具体的に書くことで、ブランク期間が自己投資の時間であったことを示せる。 |
| 家事・育児 | 令和元年6月~令和4年5月 出産・育児に専念しておりました。現在は子育ても落ち着き、就業に支障はありません。 |
誠実に理由を述べ、現在は問題なく働ける状況であることを明確に伝える。 |
| 病気療養 | 平成30年11月~令和元年10月 病気療養のため退職。現在は完治しており、医師からも就業の許可を得ております。業務への支障はございません。 |
「現在は業務に支障がない」という一文が極めて重要。採用担当者の懸念を払拭する。 |
ブランク期間は、決してマイナス要素ではありません。その期間に何を感じ、何を学び、それがこれからの仕事にどう活かせるのかを自分の言葉で語れることができれば、むしろ人間的な深みや計画性のアピールにつながります。
職歴がない・社会人未経験の場合
新卒や第二新卒、あるいは長らく専業主婦(主夫)であったなど、正社員としての職歴が全くない場合もあります。その場合は、正直に「職歴なし」と記載します。
【書き方のポイント】
- 学歴の下に「職歴」と記載: まずは基本ルール通り、学歴を書き終えたら1行空け、中央に「職歴」と見出しを書きます。
- 「なし」と記載: 次の行に、左詰めで「なし」と記載します。
- 最後に「以上」を記載: 「なし」と書いた次の行に、右詰めで「以上」と記載します。
- アルバイト経験はアピール材料: 正社員経験はなくても、パートやアルバイトの経験があれば、それを記載します(前述の「パート・アルバイトの場合」を参照)。特に応募職種と関連性があれば、強力なアピールになります。
- 自己PR欄で意欲を伝える: 職歴でアピールできない分、履歴書の「自己PR」や「志望動機」の欄で、仕事に対する熱意やポテンシャル、学習意欲などを具体的に伝えることが非常に重要です。
【見本】
職歴
なし
以上
職歴がないことを卑下する必要はまったくありません。採用担当者は、これからの成長可能性(ポテンシャル)を見ています。未経験だからこその素直さや吸収力、新しい環境への順応性を強みとしてアピールしていきましょう。
短期間で退職した場合
入社後1年未満など、短期間で退職した経歴があると、「忍耐力がないのでは」「またすぐに辞めてしまうのでは」という懸念を抱かれやすいのは事実です。しかし、書き方と伝え方次第で、その懸念を払拭することは可能です。
【書き方のポイント】
- 正直に記載する: 短期間であっても、職歴は正直に記載します。隠しても社会保険の記録でわかってしまいます。
- 退職理由は「一身上の都合」で: 履歴書には「一身上の都合により退職」と記載するのが基本です。具体的なネガティブな理由は書かないようにしましょう。
- 面接での説明を準備する: 最も重要なのは面接での説明です。なぜ短期間で辞めざるを得なかったのか、やむを得ない事情や、入社前のイメージとのギャップなどを、客観的かつ前向きな視点で説明できるように準備します。他責にするのではなく、「自身の企業研究が不足していた」といった反省点と、それを踏まえて「次の職場では長期的に貢献したい」という意欲をセットで伝えることが重要です。
- やむを得ない理由の場合は補足も可: 体調不良や家族の介護など、やむを得ない客観的な理由があった場合は、簡潔に補足することも有効です。「(体調不良のため。現在は完治しており業務に支障なし)」のように記載すると、採用担当者も納得しやすくなります。
【見本】
職歴
令和 5年 4月 株式会社ネクストキャリア 入社
人材紹介事業部に配属
令和 5年 9月 一身上の都合により退職
以上
短期間での退職経験は、次の職場選びを慎重に行うための教訓と捉えることができます。その学びをどう次のキャリアに活かすのか、という未来志向の視点で語ることで、採用担当者に納得感と成長性を感じさせることができるでしょう。
部署異動・昇進・昇格があった場合
これらは、あなたの会社での成長や評価を示すポジティブな情報です。必ず記載して、キャリアアップの過程をアピールしましょう。
【書き方のポイント】
- 時系列で記載: 異動や昇進があった年月と、新しい部署名・役職名を時系列に沿って記載します。
- 「同社」や「同部署」を活用: 同じ会社内での出来事なので、「同社」「同部署」といった言葉を使うと、すっきりと記述できます。
【見本】
職歴
平成28年 4月 株式会社スマートシステム 入社
開発第一部に配属
令和 2年 4月 同社 開発第二部に異動
令和 4年 10月 同部署 リーダーに昇格
現在に至る
以上
昇進・昇格は、あなたの能力や勤務態度が社内で認められた客観的な証拠です。リーダーシップやマネジメント経験をアピールする上で非常に有効な情報となるため、忘れずに記載しましょう。
出向していた場合
出向は、元の会社に籍を置いたまま、関連会社などで勤務する形態です。これも重要なキャリアの一部なので、正確に記載する必要があります。
【書き方のポイント】
- 在籍している会社(出向元)を基準に書く: まず、入社した会社(出向元)の情報を書きます。
- 出向の事実を明記: 出向した年月とともに、「〇〇株式会社へ出向」と記載し、出向先での部署や業務内容を続けます。出向元に戻った場合は、その年月と「出向元へ帰任」などと記載します。
【見本】
職歴
平成29年 4月 株式会社オリジン 入社
経営企画室に配属
令和 2年 4月 関連会社である株式会社オリジン・フードへ出向
新規事業開発チームにてマーケティングを担当
令和 4年 4月 株式会社オリジンへ帰任 経営企画室に再配属
現在に至る
以上
出向経験は、グループ企業内で重要な役割を任された証であり、異なる環境への適応能力や、より広い視野を持っていることのアピールにつながります。
会社の合併や社名変更があった場合
在職中に会社の組織再編(合併・買収)や社名変更があった場合、どの社名を記載すべきか迷うことがあります。採用担当者が経歴をスムーズに理解できるよう、分かりやすく記載する工夫が必要です。
【書き方のポイント】
- 入社時の社名と現在の社名を併記する: 「入社時の社名(現:現在の社名)」のようにカッコ書きで併記するのが最も分かりやすい方法です。
- 時系列で変更点を記載する: 変更があった年月を明記し、「合併により株式会社〇〇(現:△△株式会社)に社名変更」のように、事実をそのまま記載する方法もあります。
【見本】
職歴
平成28年 4月 株式会社A(現:株式会社ABホールディングス)入社
経理部に配属
令和 2年 10月 株式会社Bとの合併により、株式会社ABホールディングスに社名変更
現在に至る
以上
このように変更の経緯を記載しておくことで、採用担当者が企業情報を調べる際に混乱することがなくなります。正確な情報を提供することは、あなたの信頼性を高める上で重要です。
病気療養などで休職していた場合
業務上の傷病や私傷病により、長期間休職していた場合、その事実を履歴書に記載すべきか悩むかもしれません。基本的には、採用選考の段階で自ら休職の事実を記載する必要はありません。休職期間中も会社には在籍しているため、職歴としては途切れていないからです。
【書き方のポイント】
- 職歴欄への記載は不要: 休職は退職ではないため、職歴欄に「〇年〇月~〇年〇月 休職」などと書く必要はありません。在籍期間として通常通り記載します。
- 面接で聞かれたら正直に答える: 面接官から前職での勤務状況について深く質問され、休職の事実に触れざるを得ない場合は、正直に回答しましょう。その際、最も重要なのは「現在は完治しており、業務に支障がない」という点を明確に伝えることです。
- 健康状態申告欄がある場合: 企業によっては、応募書類に健康状態の申告欄が設けられている場合があります。その場合は、正直に現在の状況を記載する必要があります。虚偽の申告は告知義務違反にあたる可能性があるため、注意が必要です。
休職理由がポジティブなもの(産休・育休、留学など)であれば、自己PRとして記載することも考えられますが、病気療養の場合は、採用担当者に不要な懸念を与えないよう、あえて触れないのが一般的です。
会社が倒産した場合
会社の倒産や事業閉鎖は、自身の責任ではない不可抗力による退職です。そのため、その事実を明確に記載することで、採用担当者の理解を得やすくなります。
【書き方のポイント】
- 退職理由を明確に記載: 退職理由の欄に「一身上の都合」ではなく、「会社都合により退職」と記載します。
- 具体的な理由を補足: カッコ書きで「(倒産のため)」「(事業所閉鎖のため)」のように具体的な理由を補足すると、より分かりやすくなります。
【見本】
職歴
平成30年 4月 株式会社グローアップ 入社
総務部にて勤務
令和 5年 8月 会社都合により退職(倒産のため)
以上
会社都合での退職は、あなたの能力や勤務態度に問題があったわけではないことを示します。そのため、正直に記載することが、選考においてマイナスに働くことはありません。むしろ、予期せぬ事態に見舞われながらも、前向きに次のキャリアを探している姿勢は、ポジティブに評価される可能性があります。
履歴書の職歴と職務経歴書の違いとは

転職活動において、履歴書とともにもう一つ重要となるのが「職務経歴書」です。この二つの書類は、しばしば混同されがちですが、その目的と役割は明確に異なります。それぞれの違いを正しく理解し、効果的に使い分けることが、採用担当者にあなたの魅力を最大限に伝える鍵となります。
履歴書の職歴欄にどこまで書き、職務経歴書で何を補足すべきなのか。この連携を意識することで、あなたのキャリアストーリーはより説得力を増すでしょう。
【目的と役割の違い】
- 履歴書: あなたが「何者であるか」を伝えるプロフィールシートです。氏名、年齢、学歴、職歴の概要、資格といった基本的な個人情報を網羅し、応募者が募集要件を満たしているかを判断するための基礎資料となります。採用担当者はまず履歴書に目を通し、応募者の全体像を把握します。
- 職務経歴書: あなたが「何をしてきたか」「何ができるか」を具体的にアピールするプレゼンテーション資料です。これまでの業務経験、実績、培ってきたスキルなどを詳細に記述し、企業に貢献できる即戦力であることを証明する役割を担います。フォーマットは比較的自由で、自分の強みを最も効果的に見せられるように構成を工夫できます。
【記載内容の違い】
履歴書の職歴欄は、あくまで経歴の「要約」です。一方、職務経歴書は、その要約を「詳細に説明」するものです。
| 項目 | 履歴書の職歴欄 | 職務経歴書 |
|---|---|---|
| 役割 | 経歴のダイジェスト(あらすじ) | 経歴の詳細な説明(本編) |
| 記載情報 | ・在籍期間(入社・退職年月) ・会社名、部署名、役職名 ・ごく簡潔な業務内容(1~2行程度) ・退職理由(定型文) |
・職務要約(キャリアサマリー) ・所属企業ごとの詳細な業務内容 ・具体的な実績(数値を交えて) ・習得したスキル、知識(語学、PCスキル等) ・自己PR |
| 形式 | 定型フォーマット | 自由(編年体式、逆編年体式、キャリア式など) |
| 分量 | 履歴書全体の枠内(通常1/3程度) | A4用紙で1~3枚程度 |
【効果的な連携方法】
履歴書と職務経歴書は、それぞれが独立した書類ではなく、相互に補完し合う関係にあります。
- 履歴書で興味を引く: 採用担当者はまず履歴書の職歴欄を見て、あなたのキャリアの骨格を掴みます。ここで「お、この人の経験は面白そうだ」と思わせることが第一歩です。「〇〇プロジェクトのリーダーを経験」「新規事業の立ち上げに従事」といったキャッチーな経歴を簡潔に示し、興味を喚起します。
- 職務経歴書で深く理解させる: 履歴書で興味を持った採用担当者は、次に職務経歴書を読み込みます。ここで、履歴書に書いた「〇〇プロジェクト」とは具体的にどのようなもので、あなたがリーダーとしてどのようにチームをまとめ、どのような成果を出したのかを、ストーリー仕立てで詳細に説明します。具体的なエピソードや数値を交えることで、あなたの能力に説得力を持たせます。
- 書き方の具体例:
- 履歴書:
令和2年4月 株式会社デジタルシフト 入社
マーケティング部にて、ECサイトの売上向上プロジェクトを担当。 - 職務経歴書:
【職務経歴】
株式会社デジタルシフト(令和2年4月~現在)
事業内容:ECサイト運営・コンサルティング
資本金:〇〇円 従業員数:〇〇名[業務内容]
自社ECサイトのマーケティング担当として、以下の業務に従事。
・SEO対策: キーワード分析に基づき、月間20本のコンテンツ記事を企画・ディレクション。オーガニック検索からの流入数を前年比150%に向上。
・Web広告運用: Google広告、Facebook広告の運用を担当。CPAを維持しつつ、広告経由の売上を半年で30%増加。
・データ分析: Google Analyticsを用いて顧客行動を分析し、UI/UXの改善提案を実施。購入完了率を1.2%改善。
- 履歴書:
このように、履歴書で「何をしたか」のヘッドラインを示し、職務経歴書で「どのように、どれくらいの成果を出したか」を詳述することで、あなたの経験価値が立体的かつ具体的に伝わります。職歴が多い場合は、前述の通り履歴書には「詳細は職務経歴書を参照」と記載し、役割分担を明確にすることも有効な戦略です。
この2つの書類を戦略的に使い分けることが、書類選考を突破し、面接へと駒を進めるための重要なポイントとなるのです。
履歴書の職歴に関するよくある質問
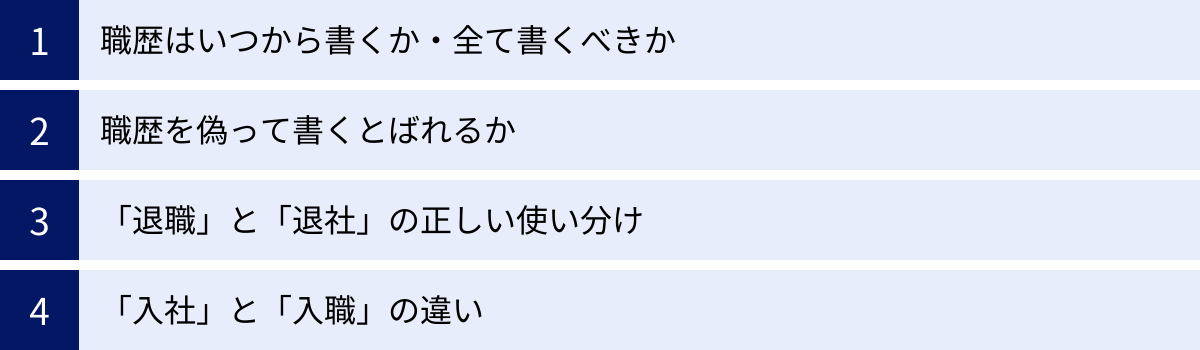
履歴書の職歴欄を作成していると、細かい点で「これはどう書くのが正しいのだろう?」と疑問が湧いてくるものです。ここでは、多くの求職者が抱きがちな質問を取り上げ、それぞれに明確な答えを提示します。これらの疑問を解消することで、迷いなく自信を持って履歴書を完成させることができるでしょう。
職歴はいつから書くべき?すべて書く必要ある?
結論から言うと、職歴は原則としてすべて正直に記載する必要があります。
これは、経歴詐称を避けるため、そしてあなたのキャリアの全体像を正確に採用担当者に伝えるためです。社会保険(厚生年金や健康保険)の加入記録は、入社手続きの際に会社側が確認するため、職歴を省略したり、在籍期間を偽ったりすると、後から必ず発覚します。これが原因で内定が取り消されたり、最悪の場合、懲戒解雇の理由になったりする可能性もあります。
【原則と例外】
- 正社員・契約社員・派遣社員の経歴: これらは雇用保険の対象となるため、すべて記載するのが義務と考えるべきです。短期間で退職した経歴であっても、正直に記載しましょう。
- パート・アルバイトの経歴: ここは少し柔軟な対応が可能です。
- 社会人経験がない、または浅い場合: 応募職種に関連するアルバイト経験は、重要なアピール材料になるため積極的に記載しましょう。
- 正社員経験が豊富にある場合: 長い正社員経験がある場合、学生時代のアルバイトや、職歴の合間に短期間だけ行ったアルバイトなどは、省略しても問題ないとされることが多いです。ただし、ブランク期間を説明するために記載するなどの戦略的な判断は必要です。
- 応募職種との関連性で判断: 例えば、長年事務職を経験してきた人が、飲食店のホールスタッフに応募する場合、過去の接客業のアルバイト経験を記載するとアピールにつながる可能性があります。「この経験は、応募先で活かせるか?」という視点で判断しましょう。
【職歴が多すぎて書ききれない場合】
前述の「転職回数が多い・職歴が書ききれない場合」の項目でも解説した通り、すべての職歴を記載した上で、業務内容の記述を工夫するのが最善策です。
- 履歴書には入社・退職の事実のみを記載する。
- 「業務内容の詳細は職務経歴書をご参照ください」と誘導する。
- 応募職種に特に関連の深い経歴のみ、1行程度の業務内容を追記してメリハリをつける。
まとめると、「職歴はすべて書く」を大原則とし、アルバイト歴の扱いは戦略的に判断する、という姿勢が最も安全かつ効果的です。
職歴を偽って書くとばれる?
はい、ほぼ100%の確率でばれると考えてください。
軽い気持ちで職歴を偽る(在籍期間を延ばす、役職を盛る、雇用形態を偽る、無職期間をなくすなど)ことは、「経歴詐称」という重大な契約違反行為です。発覚した場合のリスクは非常に大きく、絶対に避けるべきです。
【なぜばれるのか】
- 社会保険の加入記録: 会社は新しい従業員を雇用する際、年金事務所やハローワークで雇用保険や厚生年金の加入手続きを行います。その際、過去の加入履歴が明らかになるため、職歴の空白期間や在籍期間の矛盾はすぐに発覚します。
- 源泉徴収票の提出: 内定後、多くの会社では前職(または前々職)の源泉徴収票の提出を求められます。源泉徴収票には、給与を支払った会社名と支払額が記載されているため、在籍していなかった会社の名前を書いたり、在籍期間を偽ったりすると、辻褄が合わなくなります。
- リファレンスチェック(経歴照会): 応募者の同意を得た上で、前職の関係者に勤務状況や人柄などを問い合わせる「リファレンスチェック」を実施する企業が増えています。ここで虚偽の申告が発覚するケースも少なくありません。
- 面接での矛盾: 面接官は多くの応募者を見ているプロです。偽りの経歴について深く質問されると、回答に詰まったり、話に矛盾が生じたりして、嘘が見抜かれてしまいます。
- 業務遂行能力: 例えば「マネジメント経験あり」と偽って採用された場合、実際の業務でマネジメント能力が伴わなければ、すぐに周囲にわかってしまいます。
【経歴詐称のリスク】
- 内定取り消し: 入社前に発覚した場合、内定は取り消されます。
- 懲戒解雇: 入社後に発覚した場合、就業規則違反として懲戒解告の対象となります。これは最も重い処分であり、その後の転職活動にも大きな影響を及ぼします。
- 信頼の失墜: たとえ解雇されなかったとしても、社内での信頼は完全に失われます。
どんなに都合の悪い経歴であっても、正直に記載し、伝え方を工夫することが唯一の正しい道です。一時的な見栄や不安から嘘をつくことは、あなたのキャリア全体を危険に晒す行為であることを肝に銘じてください。
「退職」と「退社」の正しい使い分けは?
履歴書の職歴欄では、「退職」を使うのが正解です。
この二つの言葉は似ていますが、ニュアンスが異なります。
- 退職: 職を退くこと、会社との雇用契約を終了させること全般を指す公式な言葉です。
- 退社: この言葉には二つの意味があります。
- 「退職」と同じ意味。
- その日の業務を終えて会社から出ること(例:「本日は18時に退社します」)。
このように、「退社」には「その日の業務を終える」という意味があるため、履歴書のような公的な書類で使うと、意味が曖昧になったり、誤解を招いたりする可能性があります。どちらを使っても法的に間違いではありませんが、ビジネス文書としての正確性を期すために、雇用契約の終了を意味する場合は「退職」で統一するのが一般的かつ最も適切な表現です。
「入社」と「入職」の違いは?
一般的には「入社」を使い、特定の組織の場合に「入職」を使うと覚えておくとよいでしょう。
- 入社: 株式会社や有限会社など、一般的な営利企業(会社)に就職する場合に使います。最も広く使われる言葉です。
- 入職: 会社以外の組織・団体で働き始める場合に使われます。具体的には以下のようなケースです。
- 官公庁: 市役所、県庁、省庁など(「入庁」とも言う)
- 医療機関: 病院、クリニック、診療所など
- 福祉施設: 介護老人保健施設、特別養護老人ホームなど
- 金融機関の一部: 銀行、信用金庫、信用組合など(銀行は「入行」とも言う)
- 学校法人: 私立の学校など
- NPO法人など: 特定非営利活動法人など
自分が勤務していた組織がどのような法人格・組織形態であったかによって使い分けるのが理想です。しかし、もし迷った場合は、最も一般的な「入社」を使っておけば、大きな問題になることはありません。採用担当者も、応募者がすべての組織形態の正しい呼称を把握しているとは期待していません。ただし、例えば銀行に応募する際に、過去の銀行での経歴を「入社」と書くより「入行」と書いた方が、業界への理解度が高いという印象を与えられる可能性はあります。
履歴書作成に便利な無料ツール3選
手書きの履歴書も丁寧さが伝わりますが、PCやスマートフォンで作成すれば、修正が簡単で、複数企業に応募する際の効率も格段に上がります。最近では、会員登録不要で手軽に使えるものから、転職サイトが提供する高機能なものまで、無料で利用できる優れた履歴書作成ツールが数多く存在します。ここでは、特におすすめの無料ツールを3つ厳選してご紹介します。
(※各ツールの情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。)
① yagish(ヤギッシュ)
yagishは、とにかくシンプルで手軽に履歴書や職務経歴書を作成したい人におすすめのWebツールです。最大の魅力は、面倒な会員登録やログインが一切不要である点です。サイトにアクセスしてすぐに作成を始められ、完成した書類はPDFとしてダウンロードできます。
【特徴とメリット】
- 登録不要: 個人情報を入力することなく、誰でもすぐに利用を開始できます。プライバシーが気になる方にも安心です。
- 直感的な操作性: 画面の指示に従って項目を埋めていくだけで、自動的にきれいなフォーマットの履歴書が完成します。PC操作が苦手な人でも迷うことなく使えます。
- 職務経歴書にも対応: 履歴書だけでなく、職務経歴書の作成も可能です。転職活動に必要な書類をまとめて作成できます。
- 豊富なテンプレート: 一般的なJIS規格の履歴書はもちろん、経歴をアピールしやすい形式や、パート・アルバイト用のテンプレートも用意されています。
【注意点】
- データ保存機能なし: 会員登録がないため、作成途中のデータを保存しておくことはできません。一度ブラウザを閉じてしまうと、また最初から入力し直しになります。作成する際は、ある程度まとまった時間を確保して一気に仕上げるのがおすすめです。
手軽さとシンプルさを最優先するなら、yagishは非常に有力な選択肢となるでしょう。
参照:yagish公式サイト
② doda 履歴書ビルダー
大手転職サービス「doda」が提供する「履歴書ビルダー」は、転職活動を本格的に進めている人にとって非常に心強いツールです。dodaの会員であれば、より多くの便利な機能を利用できます。
【特徴とメリット】
- 豊富なテンプレートと例文: 履歴書・職務経歴書のテンプレートが豊富に用意されており、志望動機や自己PRの例文も多数収録されています。何を書けばいいか分からないという人の大きな助けになります。
- doda会員情報との連携: dodaに会員登録している場合、登録したプロフィール情報が自動で履歴書に反映されるため、入力の手間を大幅に削減できます。
- 選考通過者の事例を参考にできる: 実際にdodaを利用して転職に成功した人の履歴書を参考にできる機能があり、より効果的な書類作成のヒントを得られます。
- Word/Excel/PDF形式で出力: 完成した書類は、Word、Excel、PDFの3形式でダウンロード可能です。後から自分で微調整したい場合にWordやExcel形式が選べるのは大きなメリットです。
【注意点】
- 一部機能は会員登録が必要: すべての機能を最大限に活用するには、dodaへの会員登録(無料)が必要です。
手厚いサポート機能や、プロのノウハウを参考にしながら完成度の高い書類を作成したい人に最適なツールです。
参照:doda公式サイト
③ タウンワーク 履歴書アプリ
アルバイトやパート探しでおなじみの「タウンワーク」が提供する、スマートフォンでの履歴書作成に特化したアプリです。PCを持っていない人や、移動中などのスキマ時間で手軽に履歴書を作成したい場合に非常に便利です。
【特徴とメリット】
- スマホで完結: 入力から完成まで、すべての作業がスマートフォン一つで完結します。直感的なタップ操作でサクサク作成できます。
- 証明写真の撮影・加工機能: アプリ内でスマートフォンカメラを使って証明写真を撮影し、サイズ調整や背景加工まで行えます。写真を用意する手間とコストを削減できる画期的な機能です。
- 多様な提出方法: 作成した履歴書は、PDFとしてメールで送信したり、コンビニのネットプリントサービスを利用して印刷したりできます。急に履歴書が必要になった場合でも安心です。
- 入力サポート機能: 学歴の入学・卒業年度を自動で計算してくれる機能など、入力ミスを防ぐための便利なサポートが充実しています。
【注意点】
- 職務経歴書の作成には非対応: 基本的に履歴書作成に特化したアプリのため、職務経歴書を同時に作成することはできません。
スマホでの手軽さを追求し、特にアルバイト・パート応募を考えている人には、この上なく便利なアプリと言えるでしょう。
参照:タウンワーク公式サイト
| ツール名 | 運営会社 | 主な特徴 | おすすめな人 |
|---|---|---|---|
| yagish | 株式会社Yagish | 会員登録不要、シンプルな操作性、PCでの作成向き | とにかく手軽に、個人情報を登録せず作成したい人 |
| doda 履歴書ビルダー | パーソルキャリア株式会社 | 豊富な例文・テンプレート、doda会員連携、プロのノウハウ | 転職活動を本格的に行っており、質の高い書類を作成したい人 |
| タウンワーク 履歴書アプリ | 株式会社リクルート | スマホで完結、証明写真撮影機能、コンビニ印刷対応 | PCがなく、スマホだけで手軽に履歴書を作成したい人(特にアルバイト・パート応募) |
これらのツールをうまく活用することで、履歴書作成にかかる時間と労力を大幅に削減し、その分のエネルギーを企業研究や面接対策といった、より重要な活動に注力できるようになります。自分の状況や目的に合ったツールを選び、効率的に転職活動を進めていきましょう。