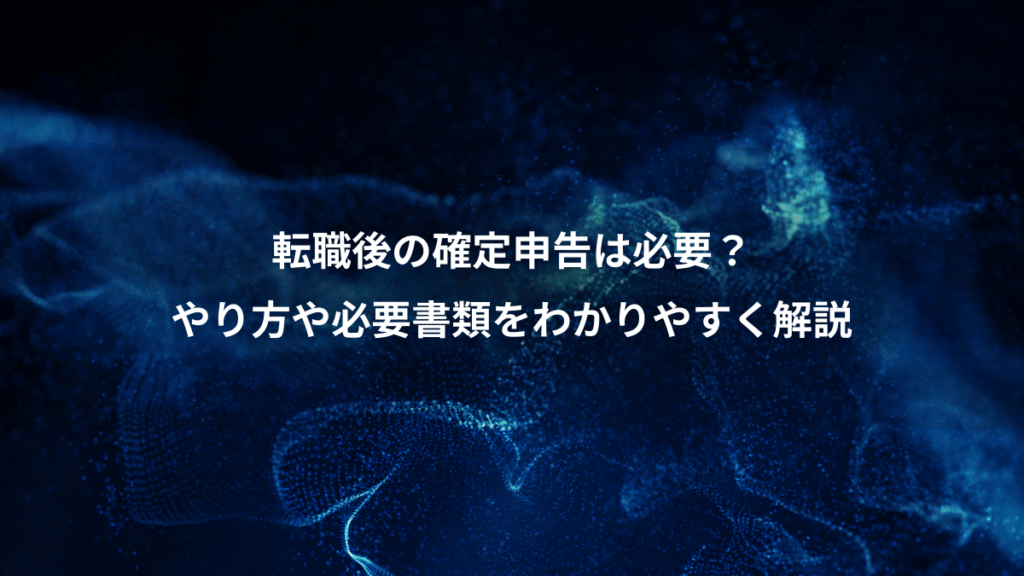転職はキャリアにおける大きな転機ですが、それに伴い様々な手続きが発生します。中でも多くの人が「自分は対象なのだろうか?」「何をすればいいのだろう?」と悩むのが「確定申告」です。
会社員であれば、通常は会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告に馴染みがない方も多いでしょう。しかし、転職した年においては、年末調整が適切に行われず、ご自身で確定申告が必要になるケースが少なくありません。
確定申告と聞くと「難しそう」「面倒だ」といったイメージがあるかもしれませんが、仕組みを理解し、手順に沿って進めれば決して難しいものではありません。むしろ、確定申告を行うことで、払いすぎていた税金が戻ってくる(還付される)可能性もあります。
この記事では、転職後の確定申告について、必要なケース・不要なケースから、具体的なやり方、必要書類、よくある質問まで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、ご自身の状況に合わせて何をすべきかが明確になり、スムーズに手続きを進められるようになるでしょう。
目次
転職後に確定申告が必要になる主なケース
まず、どのような場合に転職後の確定申告が必要になるのか、具体的なケースを見ていきましょう。ご自身の状況が以下のいずれかに当てはまる場合、確定申告を行う必要があります。
年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
会社員の場合、所得税は毎月の給与から概算で天引き(源泉徴収)され、年末に「年末調整」という手続きで正しい税額に精算されます。しかし、年の途中で会社を辞め、年末時点でどの会社にも在籍していない場合、この年末調整が行われません。そのため、自分で1年間の所得と税金を計算し、国に報告する「確定申告」が必要になります。
年内に再就職しなかったケース
例えば、3月末でA社を退職し、その年の12月31日時点でどの会社にも就職していなかったとします。この場合、A社はあなたの年末調整を行うことができません。
毎月の給与から天引きされている源泉徴収税額は、あくまで概算の金額です。生命保険料控除や扶養控除などの各種所得控除が完全に反映されていないことが多いため、年間の所得税を確定させると、源泉徴収で払いすぎていた税金が戻ってくる(還付される)ケースがほとんどです。
この還付を受けるためには、確定申告が必須となります。退職時に受け取った「源泉徴収票」をもとに、1年間の正しい所得税額を計算し、申告手続きを行いましょう。何もしなければ、払いすぎた税金は戻ってきません。
再就職したが、転職先に前職の源泉徴収票を提出していないケース
年内に再就職した場合でも、確定申告が必要になることがあります。それは、転職先の会社に、前の会社の「源泉徴収票」を提出せずに年末調整を受けてしまったケースです。
年末調整は、その年に支払われた全ての給与を合算して行う必要があります。例えば、10月にB社に転職した場合、B社は1月〜9月までに前職のA社で支払われた給与の情報がなければ、正しい年末調整ができません。そのために必要なのが、A社から発行された源泉徴収票です。
もし、源泉徴収票の提出が年末調整の期限に間に合わなかった、あるいは提出を忘れてしまった場合、転職先のB社ではB社で支払った給与(この例では10月〜12月分)のみで年末調整を行うことになります。これでは正しい税額計算ができないため、自分で前職A社の所得と現職B社の所得を合算して、確定申告を行う必要があります。
転職先の年末調整の書類提出の際に、源泉徴収票の提出を求められたかどうか、そして実際に提出したかどうかを思い出してみましょう。提出していない場合は、確定申告の対象となります。
給与以外の所得が年間20万円を超える場合
会社員としての給与以外に、副業などで所得を得ている場合も確定申告が必要になることがあります。ポイントは、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が年間で20万円を超えるかどうかです。
ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」である点です。所得とは、収入からその収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた金額を指します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 収入 | 副業などで得た売上全体の金額 |
| 必要経費 | 収入を得るために直接かかった費用(例:仕入代、PC購入費、通信費など) |
| 所得 | 収入 – 必要経費 |
例えば、以下のようなケースでは確定申告が必要です。
- 具体例1:Webライターの副業
- 年間の執筆料収入:50万円
- 必要経費(PC購入費、書籍代、通信費など):15万円
- 所得:50万円 – 15万円 = 35万円 (> 20万円) → 確定申告が必要
- 具体例2:インターネットでの商品販売
- 年間の売上:100万円
- 必要経費(仕入代、送料、梱包材費など):85万円
- 所得:100万円 – 85万円 = 15万円 (≦ 20万円) → 原則として所得税の確定申告は不要
- ※ただし、所得が20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。確定申告を行えば住民税の申告も兼ねることができるため、手続きを一本化したい場合は確定申告を行うのがおすすめです。
対象となる所得には、原稿料や業務委託報酬などの「雑所得」や「事業所得」、アパート経営などによる「不動産所得」など、さまざまな種類があります。転職を機に副業を始めた方などは、この基準に当てはまるか確認しましょう。
2か所以上から給与をもらっている場合
正社員として働きながらアルバイトを掛け持ちしている場合など、2か所以上の会社から給与を受け取っている場合も、原則として確定申告が必要です。
年末調整は、原則として1人の従業員に対して1つの会社でしか行うことができません。通常は、メインの給与を受け取っている会社(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している会社)で年末調整を行います。
しかし、その年末調整には、もう一方の会社から受け取っている給与の情報は含まれていません。そのため、年末調整が行われなかったサブの会社の給与所得と、メインの会社の給与所得を合算して、自分で確定申告を行い、所得税を再計算・納税する必要があります。
ただし、年末調整されなかった方の給与収入の合計額が年間20万円以下である場合は、確定申告は不要とされています。しかし、この場合も住民税の申告は別途必要になるため注意が必要です。
医療費控除やふるさと納税などの控除を受けたい場合
ここまでは確定申告が「義務」となるケースを説明してきましたが、自ら申告することで税金の還付を受けられる「権利」としての確定申告もあります。
年末調整でも生命保険料控除や地震保険料控除などは申請できますが、以下の控除は年末調整では対応できないため、確定申告が必要です。
- 医療費控除:
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や生計を一つにする家族のために支払った医療費の合計が原則として10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除です。治療費だけでなく、通院のための交通費(公共交通機関)や、医師の指示による医薬品の購入費なども対象になります。 - 寄附金控除(ふるさと納税など):
ふるさと納税を行った場合、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税から控除が受けられます。「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告は不要ですが、寄付した自治体が6か所以上ある場合や、もともと医療費控除などで確定申告が必要な場合は、この制度は利用できず、確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。 - 住宅ローン控除(1年目):
住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した場合に受けられる税額控除です。適用を受ける最初の年だけは、必ず確定申告が必要です。2年目以降は、会社の年末調整で手続きができます。 - 雑損控除:
災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に受けられる所得控除です。
これらの控除を利用したい場合は、たとえ転職先で年末調整が完了していたとしても、ご自身で確定申告を行いましょう。
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職金を受け取った場合、通常は退職する会社に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出します。これを提出すると、会社側が退職所得控除という大きな控除を適用した上で所得税を計算・源泉徴収してくれるため、課税関係はそれで完結します。
しかし、何らかの理由でこの申告書を提出せずに退職金を受け取った場合、退職金の支払額に対して一律20.42%の税率で源泉徴収されてしまいます。この場合、退職所得控除が適用されていないため、非常に高い税金を支払っている状態になります。
この払いすぎた税金を取り戻すためには、確定申告が必須です。 確定申告で正しく退職所得を申告し直すことで、多額の税金が還付される可能性があります。退職金を受け取った方は、この申告書を提出したかどうかを必ず確認しましょう。
転職後に確定申告が不要なケース

次に、確定申告が不要となるケースについて解説します。ご自身の状況がこちらに当てはまれば、原則として何もしなくても問題ありません。
転職先で年末調整が完了している場合
確定申告が不要になる最も一般的でシンプルなケースは、転職先で年末調整が適切に完了している場合です。
具体的には、以下の条件をすべて満たしている状態を指します。
- 年内に再就職していること:
前の会社を辞めた後、同じ年の12月31日までに新しい会社に入社している。 - 転職先に前職の源泉徴収票を提出していること:
前の会社から発行された「源泉徴収票」を、転職先の年末調整の担当部署(経理や人事など)に期限内に提出している。
この2つの条件を満たしていれば、転職先の会社が、前職の給与と自社で支払った給与を合算したうえで、1年間の正しい所得税を計算し、年末調整を行ってくれます。これにより所得税の精算が完了するため、個人で確定申告を行う必要はなくなります。
年末調整の時期(通常11月〜12月頃)に、会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」といった書類の記入を求められ、前職の源泉徴収票と一緒に提出したのであれば、このケースに該当する可能性が高いです。
年末調整で対応できない控除の申請が不要な場合
上記の「転職先で年末調整が完了している」という条件を満たしていても、確定申告が必要になるケースがあることは前述の通りです。それは、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しない場合)など、年末調整では手続きできない控除を適用したい場合です。
裏を返せば、これらの年末調整では対応できない控除を特に申請する必要がないのであれば、確定申告は不要ということになります。
例えば、以下のような状況であれば、転職先で年末調整が完了していれば、それ以上の手続きは必要ありません。
- 年間の医療費が10万円以下だった。
- ふるさと納税をしていない、または「ワンストップ特例制度」を利用する条件を満たしている(寄付先が5自治体以内、かつ他に確定申告の必要がない)。
- 住宅ローン控除の対象ではない、または2年目以降で年末調整で手続きしている。
つまり、給与以外の所得がなく、特別な控除の申請も必要なく、転職先で前職分も合算して年末調整をしてもらっていれば、確定申告は不要と覚えておきましょう。
転職後の確定申告に必要な書類
確定申告を行うことを決めたら、次に必要な書類の準備に取り掛かります。書類には全員が必ず準備するものと、特定の控除を受けるために必要なものがあります。漏れがないように、一つずつ確認していきましょう。
全員が準備する書類
以下の書類は、確定申告を行うすべての方が基本的に必要となるものです。
確定申告書
確定申告を行うためのメインの書類です。以前は「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類がありましたが、令和4年分以降は様式が一本化され、A・Bの区別はなくなりました。
主な入手方法
- 国税庁のウェブサイトからダウンロード: PDFファイルをダウンロードして印刷し、手書きで作成できます。
- 税務署の窓口で受け取る: お近くの税務署や市区町村の役所(確定申告の時期)で入手できます。
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」で作成: ウェブサイト上で必要事項を入力すると、自動で計算・作成されます。印刷して提出することも、そのまま電子申告(e-Tax)することも可能です。初心者にはこの方法が最もおすすめです。
参照:国税庁ウェブサイト
源泉徴収票
転職後の確定申告において、最も重要な書類の一つです。1年間に支払われた給与の総額、源泉徴収された所得税額、社会保険料の金額などが記載されています。
- 年の途中で退職し、再就職していない場合: 退職した会社から発行された源泉徴収票が必要です。
- 再就職したが、年末調整を受けていない場合: 前職の会社と、現在勤めている転職先の会社、両方の源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票は、通常、退職後1ヶ月以内、または年末調整後(12月〜1月頃)に会社から交付されます。もし手元にない、紛失してしまったという場合は、速やかに会社の経理や人事担当者に連絡し、再発行を依頼しましょう。
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
申告者が本人であることを確認し、マイナンバー(個人番号)を証明するための書類です。マイナンバーカードの有無によって必要な書類が異なります。
| 必要な書類 | |
|---|---|
| マイナンバーカードがある場合 | マイナンバーカードのコピー(表面・裏面の両方) |
| マイナンバーカードがない場合 | 【番号確認書類】 通知カードのコピー、またはマイナンバー記載の住民票の写しなど 【身元確認書類】 運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険証などのコピー |
マイナンバーカードがない場合は、「番号確認書類」と「身元確認書類」の2種類を準備する必要がありますので注意しましょう。e-Taxで申告する場合は、これらの書類の提示や提出は不要です。
還付金の振込先口座がわかるもの
確定申告の結果、税金が還付される(戻ってくる)場合に、その還付金を振り込んでもらうための口座情報が必要です。申告者本人名義の預貯金口座の通帳やキャッシュカードを準備し、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかるようにしておきましょう。
対象者のみ準備が必要な書類(控除用)
各種控除を受けるためには、その支払いを証明する書類を添付または提示する必要があります。ご自身が利用したい控除に合わせて準備しましょう。
医療費控除の明細書
医療費控除を受ける際に必要です。支払った医療費の領収書を一枚一枚提出するのではなく、「医療費控除の明細書」に支払先や金額などをまとめて記入して提出します。この明細書の様式は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。なお、医療費の領収書は提出不要ですが、自宅で5年間保管する義務があります。
健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付すると、明細の記入を一部省略できて便利です。
寄附金受領証明書(ふるさと納税など)
ふるさと納税で寄附金控除を受ける場合に必要です。寄付先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を準備します。複数の自治体に寄付した場合は、すべての証明書が必要です。
生命保険料・地震保険料の控除証明書
生命保険や地震保険に加入している場合、保険料に応じて所得控除が受けられます。通常は会社の年末調整で申告しますが、提出し忘れた場合や、年末調整を受けていない場合は、確定申告で申請します。毎年秋頃に保険会社から郵送で届く「控除証明書」(ハガキや封書)が必要です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金払込証明書
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になります。年末調整で申告し忘れた場合などは、確定申告で申請します。国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を準備しましょう。
国民年金保険料・国民健康保険料の支払額がわかる書類
退職後、次の会社に入社するまでの期間に国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を支払った場合に必要です。これらの保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
- 国民年金保険料: 日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
- 国民健康保険料: 自治体によって扱いが異なりますが、年間の支払額がわかる納付済確認書や、支払った際の領収書などを準備します。証明書の添付義務はありませんが、支払額を正確に記入するために必要です。
転職後の確定申告のやり方4ステップ
必要書類が揃ったら、いよいよ確定申告の手続きを進めていきます。全体の流れは大きく4つのステップに分かれます。一つずつ着実に進めていきましょう。
① 必要な書類を揃える
最初のステップは、前章で解説した必要書類をすべて集めることです。これが最も重要で、時間がかかる可能性のあるステップです。
【準備する書類のチェックリスト】
- (全員)確定申告書
- (全員)源泉徴収票(前職分、必要であれば現職分も)
- (全員)本人確認書類(マイナンバーカード or 通知カード+身元確認書類)
- (全員)還付金の振込先口座がわかるもの
- (対象者のみ)各種控除証明書(医療費、寄附金、保険料など)
- (対象者のみ)国民年金・国民健康保険の支払額がわかるもの
特に、源泉徴収票が手元にない場合は、早めに前の会社に再発行を依頼してください。 発行に時間がかかることもあるため、申告期限ギリギリになって慌てないよう、余裕を持った行動が大切です。他の控除証明書なども、ファイルにまとめて整理しておくと、後の作業がスムーズになります。
② 確定申告書を作成する
書類が揃ったら、確定申告書を作成します。主な作成方法は以下の通りです。
- 手書き: 税務署や国税庁サイトから入手した申告書用紙に、鉛筆やボールペンで直接記入します。計算も自分で行う必要があります。
- 会計ソフトを利用: 市販の会計ソフトやクラウドサービスを利用して作成します。日々の収支を記録している副業がある方などに便利です。
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」を利用: 初心者の方に最もおすすめの方法です。パソコンやスマートフォンの画面に表示される案内に従って、源泉徴収票や控除証明書の内容を入力していくだけで、税額が自動計算され、申告書が完成します。入力ミスや計算間違いを防げるため、非常に便利で安心です。
「確定申告書等作成コーナー」では、源泉徴収票を見ながら「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」といった項目を対応する入力欄に転記していく作業が中心となります。医療費控除などの計算も画面上で簡単に行えるため、専門知識がなくても直感的に進めることが可能です。
③ 期間内に税務署へ提出する
完成した確定申告書は、期間内に税務署へ提出します。提出先は、申告を行う年の12月31日時点ではなく、申告書を提出する時点での住所地を管轄する税務署です。引越しをした方は注意しましょう。
提出方法には、主に以下の3つがあります。それぞれのメリット・デメリットを考慮して、自分に合った方法を選びましょう。
- e-Tax(電子申告)で提出する
- 税務署の窓口へ直接持参する
- 郵便または信書便で税務署に送付する
各提出方法の詳細は、次の「確定申告書の作成・提出方法3選」で詳しく解説します。
提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。この期間を過ぎてしまうとペナルティが課される可能性があるため、必ず期限内に提出しましょう。
④ 税金を納付または還付を受ける
申告書の提出後、計算結果に応じて税金を納付するか、還付金を受け取ります。
- 納付する場合(納税):
確定申告の結果、追加で納める税金が発生した場合は、申告期限と同じ3月15日までに納付する必要があります。主な納付方法は以下の通りです。納付方法 概要 振替納税 指定した預貯金口座から自動で引き落とされる。事前に届出が必要。 e-Tax(電子納税) インターネットバンキングやダイレクト納付を利用して電子的に納付。 クレジットカード納付 専用サイトを通じてクレジットカードで納付。決済手数料がかかる。 QRコードによるコンビニ納付 申告書作成時に発行されるQRコードを使い、コンビニの窓口で納付。 現金納付 金融機関や税務署の窓口で、納付書を添えて現金で納付。 -
還付を受ける場合(還付):
払いすぎた税金が戻ってくる場合は「還付申告」となり、特別な手続きは不要です。申告書に記載した銀行口座に、後日、国(税務署)から還付金が振り込まれます。
振込までにかかる期間の目安は、e-Taxで提出した場合は2〜3週間程度、書面で提出した場合は1ヶ月〜1ヶ月半程度です。早く還付金を受け取りたい場合は、e-Taxでの申告が有利です。
確定申告書の作成・提出方法3選
確定申告書の提出方法は、ご自身のITスキルや時間の使い方、安心感の求め方によって最適なものが異なります。ここでは、代表的な3つの方法のメリットとデメリットを詳しく解説します。
① スマホやPCで完結する「e-Tax」
e-Tax(イータックス)は、国税に関する申告や納税などの手続きをインターネット経由で行えるシステムです。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告データを、そのままオンラインで送信できます。現在、国が最も推奨している方法です。
- メリット:
- 24時間いつでも提出可能: 税務署の開庁時間を気にする必要がなく、自宅や好きな場所から自分のタイミングで提出できます。
- 還付がスピーディー: 書面提出に比べ、還付金が振り込まれるまでの期間が短縮されます(通常2〜3週間程度)。
- 添付書類の一部が提出不要: 生命保険料控除証明書や医療費の明細書など、一部の第三者作成書類は、記載内容を入力して送信すれば提出を省略できます(ただし、5年間の保管義務はあります)。
- 移動の手間とコストが不要: 税務署に行くための交通費や郵送代がかかりません。
- デメリット:
- 事前準備が必要: マイナンバーカードと、それを読み取るためのスマートフォンまたはICカードリーダライタが必要です。(ID・パスワード方式もありますが、暫定的な措置とされています)。
- 操作に慣れが必要: 初めて利用する際は、初期設定や操作方法に少し戸惑うかもしれません。
総合的に見て、時間や場所の制約を受けずに効率的に手続きを済ませたい方には、e-Taxが最もおすすめの方法です。
② 税務署の窓口に直接提出する
作成した確定申告書と必要書類一式を、管轄の税務署の窓口に直接持参して提出する方法です。昔ながらの確実な方法と言えます。
- メリット:
- 安心感がある: 職員に直接手渡すため、提出したことが明確で安心感があります。
- その場で質問できる: 書類の書き方などで不明な点があれば、確定申告会場に設置されている相談窓口で質問できます(ただし、長蛇の列ができることもあります)。
- 受付印をもらえる: 提出する申告書の控えを持参すれば、その場で収受日付印(受付印)を押してもらえます。この控えは、住宅ローンの審査などで所得証明として必要になる場合があります。
- デメリット:
- 非常に混雑する: 確定申告期間中、特に期限間際の税務署は大変混雑し、長時間待たされることが珍しくありません。
- 開庁時間が限られる: 平日の日中(通常8:30〜17:00)に行く必要があります。
- 移動の手間がかかる: 税務署までの移動時間と交通費がかかります。
なお、税務署に設置されている「時間外収受箱」に投函すれば、閉庁後や土日でも提出は可能です。ただし、その場で内容のチェックや質問はできません。
③ 郵便で税務署に送付する
作成した確定申告書と添付書類を、管轄の税務署宛に郵送する方法です。
- メリット:
- 税務署の混雑を避けられる: 自分の都合の良い時間に郵便局やポストから発送できます。
- 移動の手間が少ない: 税務署が遠い場合でも、郵送で済ませることができます。
- デメリット・注意点:
- 「信書」として送る必要がある: 確定申告書は「信書」にあたるため、必ず「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送る必要があります。宅配便、ゆうパック、ゆうメールなどでは送れません。
- 消印の日付が提出日となる: 提出期限である3月15日の通信日付印(消印)が押されていれば、期限内提出として認められます。しかし、郵便局の集荷時間などを考慮し、余裕を持って発送することが重要です。
- 受付印付きの控えが必要な場合: 控えに受付印が欲しい場合は、申告書の控え一部と、自分の住所・氏名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。このひと手間を忘れないようにしましょう。
確定申告はいつからいつまで?

確定申告には厳密な期間が定められています。義務のある申告と、権利である還付申告では期間が異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
確定申告の期間
所得税および復興特別所得税の確定申告の期間は、原則として、申告対象の年の翌年2月16日から3月15日までです。
例えば、2023年(令和5年)に転職し、確定申告が必要になった場合、申告期間は2024年(令和6年)2月16日から3月15日までとなります。
この期間は、税金を納付する必要がある方、あるいは給与以外の所得が20万円を超えるなどの理由で申告が義務付けられている方のための期間です。納税が必要な場合の納付期限も、同じく3月15日です。
期限日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その翌開庁日が期限日となります。期限を過ぎるとペナルティが課される可能性があるため、期間厳守が絶対です。
払いすぎた税金の還付申告ができる期間
一方、確定申告の義務はないものの、医療費控除や年の途中での退職により、払いすぎた税金を取り戻すために行う申告を「還付申告」といいます。
この還付申告は、前述の2月16日〜3月15日の期間に限定されません。還付申告の対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出することが可能です。
例えば、2023年(令和5年)分の還付申告は、2024年(令和6年)1月1日から2028年(令和10年)12月31日まで行うことができます。
還付申告であれば、税務署が混雑する2月16日〜3月15日を避けて、年明けすぐの空いている時期に手続きを済ませることができるという大きなメリットがあります。ご自身の申告が還付申告のみに該当する場合は、早めに手続きを済ませてしまうのがおすすめです。
転職後の確定申告に関するQ&A
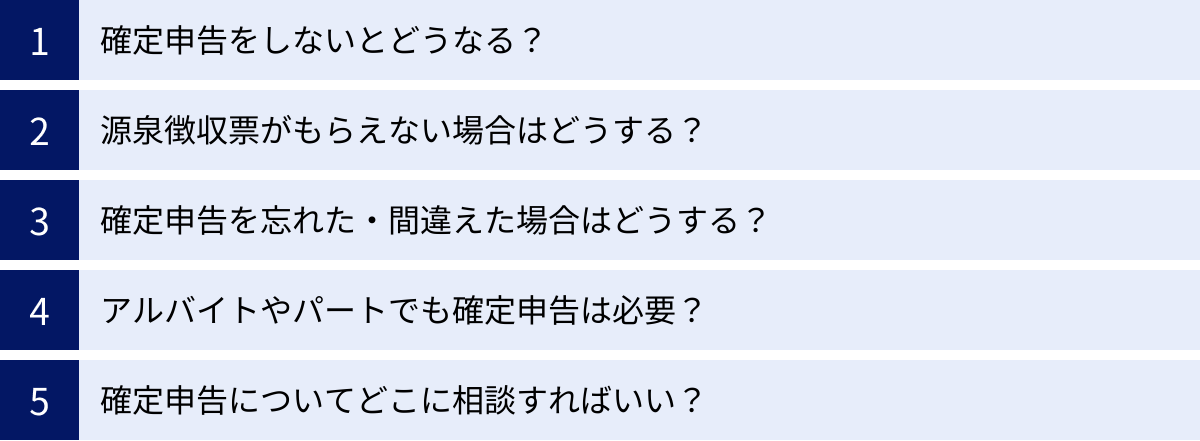
最後に、転職後の確定申告に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で解説します。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告が必要な義務があるにもかかわらず、期限内に申告をしなかった場合、いくつかのペナルティが課されます。
無申告加算税が課される
本来納めるべき税額に加えて、ペナルティとして「無申告加算税」が課されます。 税率は、納付すべき税額によって異なり、原則として以下の通りです。
- 納付税額のうち50万円までの部分:15%
- 納付税額のうち50万円を超える部分:20%
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、この税率が5%に軽減されることがあります。
参照:国税庁ウェブサイト
延滞税が発生する
法定納期限(原則3月15日)の翌日から、税金を完納する日までの日数に応じて、利息に相当する「延滞税」も発生します。 延滞税の税率は年によって変動しますが、納付が遅れれば遅れるほど、支払う金額は雪だるま式に増えていきます。
確定申告を怠ることは、金銭的に大きな不利益を被ることに繋がります。申告義務がある場合は、必ず期間内に手続きを行いましょう。
前の会社の源泉徴収票がもらえない場合はどうする?
会社は、退職した従業員に対して、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を交付する義務があります(所得税法第226条)。しかし、万が一もらえない、または紛失してしまった場合は、以下の手順で対応しましょう。
- まずは前職の会社に丁重に再発行を依頼する:
まずは経理や人事の担当者に連絡を取り、源泉徴収票の発行または再発行をお願いするのが第一歩です。ほとんどの場合はこれで解決します。 - 「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出する:
会社に依頼しても応じてもらえない、連絡がつかないといった悪質なケースでは、所轄の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出するという手段があります。この届出書を提出すると、税務署から会社に対して行政指導が行われ、源泉徴収票の発行を促してくれます。この手続きの際には、給与明細書のコピーなど、給与額がわかる書類の添付を求められることがあります。
給与明細書があれば、そこに記載された情報をもとに確定申告を進めることも可能ですが、正確性を期すためにも、源泉徴-収票を入手するのが最善です。
確定申告を忘れた・間違えた場合はどうする?
うっかり申告を忘れてしまったり、提出後に間違いに気づいたりすることもあるかもしれません。その場合の対処法を知っておけば、慌てずに行動できます。
- 申告を忘れていた場合(期限後申告):
気づいた時点ですぐに申告手続きを行いましょう。これを「期限後申告」といいます。前述の無申告加算税や延滞税はかかってしまいますが、放置するよりもはるかに損害を抑えられます。 - 税額を多く申告してしまった場合:
還付されるべき税金が少なかった、あるいは納める税金が多すぎたという場合は、「更正の請求」という手続きを行うことで、払いすぎた税金の還付を求めることができます。この手続きは、法定申告期限から5年以内に行うことができます。 - 税額を少なく申告してしまった場合:
納めるべき税金が少なかったことに気づいた場合は、「修正申告」という手続きを行います。自ら誤りを訂正し、不足分の税金を納付します。税務署から指摘される前に自主的に修正申告をすれば、ペナルティである「過少申告加算税」は課されません(ただし、延滞税は発生します)。
いずれのケースでも、気づいた時点ですぐに行動することが最も重要です。
アルバイトやパートでも確定申告は必要?
確定申告が必要かどうかは、雇用形態(正社員、アルバイト、パートなど)ではなく、所得の状況によって決まります。 そのため、アルバイトやパートの方でも、正社員と同じ条件に当てはまれば確定申告が必要です。
- 掛け持ちしている場合:
2か所以上から給与をもらっており、年末調整されなかった方の給与収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。 - 年の途中で辞めた場合:
アルバイト先を年の途中で辞め、年末調整を受けていない場合も確定申告が必要です。源泉徴収で税金が天引きされていれば、申告することで還付される可能性があります。 - 年収103万円以下の場合:
年間の給与収入が103万円以下であれば、所得税はかかりません。もし給与から源泉徴収されている場合は、確定申告をすればその全額が還付されます。
確定申告についてどこに相談すればいい?
手続きでわからないことが出てきた場合、専門家に相談するとスムーズに解決できます。主な相談先は以下の2つです。
税務署
確定申告に関する最も基本的な相談先です。国税庁のウェブサイトには「タックスアンサー」というよくある質問集があり、電話での相談センターも設置されています。また、確定申告期間中には、税務署内に無料の相談会場が設けられます。
一般的な手続きの方法や書類の書き方などを聞きたい場合に適しています。 ただし、個別の節税対策といったコンサルティング的な相談には応じてもらえません。
税理士
税理士は税金のプロフェッショナルです。個別の複雑な事情がある場合や、最適な節税方法を知りたい、あるいは申告書の作成・提出自体を代行してほしいといった場合に頼りになります。
もちろん相談や依頼には費用が発生しますが、専門的な視点から的確なアドバイスを受けられるという大きなメリットがあります。初回相談は無料としている税理士事務所も多いため、まずはそうしたサービスを利用してみるのも良いでしょう。
自分一人で抱え込まず、必要に応じてこれらの相談先をうまく活用することが、確実な申告への近道です。